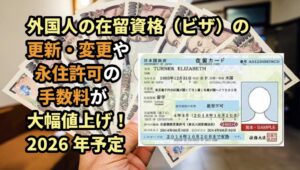(更新者:国際行政書士 河野尋志)
「定住者ビザ」とは、日本の法務大臣が外国人の方お一人おひとりの特別な理由を考慮して、一定の期間を指定して日本での居住を認める在留資格(ビザ)です。永住ビザと同じく就労制限がない(法律の範囲内であればどんな仕事でもできる)というメリットはありますが、永住ビザと違い、在留期間の制限があります。
定住者ビザは「日本の法務省の告示によって定められているもの(告示内)」と「それ以外の告示に該当しないもの(告示外)」の2種類に分けられます。
定住者ビザについて解説します
告示内の「定住者ビザ」の具体例
告示によって定められている内容(告示内)は以下です。
- 定住者告示1号(難民)
- 定住者告示2号(削除)
- 定住者告示3号(日系2世・日系3世)
- 定住者告示4号(告示3号以外の日系3世)
- 定住者告示5号(定住者の配偶者)
- 定住者告示6号(未婚で未成年の実子)※いわゆる連れ子定住を含む
- 定住者告示7号(6歳未満の養子)
- 定住者告示8号(中国残留孤児関係)
※告示の内容につきまして詳しくは以下をご参照ください。
以下では、告示内「定住者ビザ」 の事例をご紹介します。
告示内「定住者ビザ」 の事例 ❶
日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合(定住者告示6号)(定住者告示7号)
日本人と国際結婚された外国人配偶者の出身国にお子さん(連れ子)がいて、呼び寄せる(在留資格「認定」証明書交付申請=COE)場合です。
まず「実子」の場合の条件は、子供が未成年(18歳未満、つまり17歳まで)で、未婚(結婚していない)であることが条件です。そのため18歳以上になっている場合は「未成年・未婚の実施」として定住者ビザでは日本に呼べません。また、基本的に子供の年齢が高くなるほど自分で生活できる能力があると判断されやすく、特に15歳以上になると不許可になる可能性が上がり、呼び寄せは難しくなる傾向にあります。
次に「養子」の場合の条件は、子供が6歳未満(つまり5歳まで)に限られます。6歳以上であっても与えられる可能性もある、という情報もありますが、「本国に養育看護する者がいない」など特別な場合に限られ、それをしっかり証明する必要があります。
告示内「定住者ビザ」 の事例 ❷
日系の外国人の方が、就労制限がない定住者ビザを取得する場合(定住者告示3号・4号)
日系の外国人の方は、南米のご出身者の方が多いです。日系ブラジル人や日系ペルー人などといわれる方々です。日本にはブラジル人街と呼ばれる地域もあるくらいです。
日系の外国人の方は、日系3世、場合によっては4世まで定住者ビザの取得が可能です。定住者ビザは就労制限がないので、どんな職種でも働くことができます。ビザ取得に学歴なども関係ありません。ただし、日系の外国人であることを証明するために、戸籍謄本や除籍謄本を探し出して、先祖が日本人だったことを証明する必要があります。

河野
(かわの)
ご不明点あればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。
告示外の「定住者ビザ」の具体例
次に、告示外の定住者ビザをご紹介します。告示外の定住者ビザは、外国人の方の「特別な理由」から認められるビザなので、非常に多くの場合があります。場合によっては「人道的な観点」で許可をする性格もありますので、入国管理局から個別具体的な許可や審査基準は明らかにされいません。以下では、現状で分かっている範囲の「7つ告示外定住ビザ」をご紹介します。
- 【離婚定住】
- 【死別定住】
- 【日本人実子扶養定住】
- 【婚姻破綻定住】
- 【特別養子離縁定住】
- 【難民不認定定住】
- 【看護養育】
以下では、告示内「定住者ビザ」 の事例をご紹介します。
告示外「定住者ビザ」 の事例 ❶
【離婚定住】【死別定住】
配偶者ビザを持って日本に在留していた外国人の方が、日本人と離婚か、または不幸にも死別してしまったときに、そのまま日本に在留するために「定住者ビザ」に変更できる可能性があります。
●まず忘れずに「届出」を!
離婚または死別してしまった場合、まずは2週間以内に忘れずに入国管理局へ行き、離婚した旨の「届出」をしなければなりません。「つらい状況だったから、そんなこと忘れていた」というお気持ちはよく分かりますが、この届出が遅れると今後のビザ申請の審査に影響がある可能性がありますので、必ず届出をしましょう。
●6ヶ月以内にビザ変更する必要があります
配偶者ビザを持っている外国人の方でも、日本人と離婚または死別してしまうと、そのままの状態では、配偶者ビザで日本に在留することができませんので、帰国しなければならない可能性が高くなります。まだビザの在留期間が残っていたとしても、6ヶ月以内に別のビザへ変更する必要があります。
●日本国籍のお子さん(実子)がいるかいないかが重要
離婚または死別してしまった場合、日本国籍のお子さん(実子)がいるかいないかが非常に大きなポイントになります。日本国籍のお子さんがいる場合は、結婚期間が1年程度でも定住者ビザが許可される可能性があります。ただし、お子さんを本国の親に預ける場合は、子供の養育を理由とした定住者ビザへ変更はできません。
●他のビザへ変更できる可能性もあります
別のビザへ変更できる場合もあります。例えば、就職して就労系ビザ(技人国、特定技能、経営管理など)を許可された場合です。もちろん、他の日本人と再婚した場合は配偶者ビザを許可される可能性もあります。
●「同居した結婚期間」が最低3年以上
仮に日本国籍のお子さん(実子)がいない場合でも、配偶者ビザで3年以上日本に在留していたのであれば、離婚しても「定住者ビザ」へ変更ができる可能性があります。もちろん、定住者ビザも申請後に審査がありますので「理由書」が非常に重要になります。「なぜ日本にいたいのか」「生計はどのようにしていくのか(収入はあるか)」など、しっかりと合理的に「理由書」で説明しましょう。最近では日本人配偶者によるDV被害が原因で離婚してしまった場合には、定住者ビザが認められる可能性も高くなっています。
※【定住者ビザが許可される要件】以下の全てに該当していること
●日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
●生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
●日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
●公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
【 審査のポイント❶ 】
通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたこと(正常な婚姻関係・家庭生活)が重要です。別居していた期間があったとしても、夫婦としてお互いに援助し合っていたこと、しっかり交流が継続していたと認められれば、問題ありません。
【 審査のポイント❷ 】
「日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでない」とは、例えば、申請書に記載された日本語文章や、面接の際に外国人の方との意思疎通が可能であれば問題ないと判断されます。特定の日本語の試験(日本語能力試験など)に合格していることまでは問わない、とされています。
【 審査のポイント❸ 】
離婚や死別した配偶者が日本人ではなく「定住者ビザ」の外国人の方の場合、許可される可能性はゼロではありません。ただし、離婚や死別した配偶者が「日本人」「永住者」「特別永住者」だった場合と比べると、許可される可能性が低くなるのが現実です。
告示外「定住者ビザ」 の事例 ❷
【日本人実子扶養定住】
「日本人実子」とは、お子さんが生まれたときに、父母のどちらかが日本国籍を持つ人、ということです。お子さん自身が日本国籍を持っていなくても大きな問題はありません。重要なのは日本でお子さんと一緒に暮らして育てている(扶養している)ことです。
※【定住者ビザが許可される要件】以下の全てに該当していること
●生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
●日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれかに該当すること
・日本人の実子の親権者であること
・現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること
【 審査のポイント❶ 】
日本国籍を有しない非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものこと。「婚外子」とも呼ばれます)については、日本人の父から「認知」されていることが必要です。
【 審査のポイント❷ 】
親権者(外国人の親)が未成年者(18歳未満のお子さん)を監督し、保護していること(監護・養育)が重要です。また、仮に定住者ビザが許可されても、ビザ更新の際に、実際に監護・養育していないことが分かれば更新申請は不許可となる可能性が高くなります。(お子さんが就労開始又は婚姻により独立した場合を除く。)
【 審査のポイント❸ 】
生計を営むに足りる資産又は技能を有する(日本で生活できるだけの収入がある)ことが要件ですが、外国人の親に、収入を得ることが難しい事情があり生活保護等が支給されている場合でも、将来的には働く意思があり、お子さんを監護・養育している事実が確認できれば、「生計を営むに足りる資産又は技能を有しないもの」にはなりません。ただし、近い将来、生活保護等をもらわずに、働くための予定や計画を「理由書」にしっかり誠実に記載することが重要です。
更に詳しくは以下の記事をご覧ください。
告示外「定住者ビザ」 の事例 ❸
【婚姻破綻定住】
「日本人」や「永住者」「特別永住者」と結婚して配偶者ビザを持っているけれど、その婚姻が事実上破綻しても(結婚していないのと同じ状態が続いていても)、引き続き日本に在留を希望する外国人の方が対象です。
※【定住者ビザが許可される要件】
以下の次の❶又は❷に該当し、更に❸と❹の両方にする該当していれば対象になります。
❶ 日本において3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと分かる
❷ 正常な婚姻関係・家庭生活が継続後に、DV(例えば配偶者から振るわれる暴力)による被害を受けたと認められる者
❸ 生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
❹ 公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
【 審査のポイント❶ 】
「婚姻が事実上破綻」しているとは、婚姻は継続中(離婚はしないない)だが、夫婦の両方に婚姻継続の意思がなくなり、同居しておらず、お互いに協力する活動もなく、その状態が続いていることが誰の目にも明らかで、婚姻関係に戻る可能性がない場合などを意味します。
【 審査のポイント❷ 】
婚姻破綻とまでは認められない場合は、今持っている配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザ)の在留資格で更新できる可能性があります。
更に詳しくは以下の記事をご覧ください。

河野
(かわの)
ご不明点あればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。
「定住者ビザ」の取得要件と必要書類について
同じ「定住者ビザ」でも、告示内や告示外など種類が多く、申請人がどの状況に該当するかによって要件も大きく異なってくるので、満たすべき要件や用意するべき書類が異なります。
特に、告示外については、明確な要件や必要書類が定められていないので注意が必要です。
【定住者ビザ 告示外定住 番外編】
「告示外定住」については外国からの呼び寄せ(在留資格「認定」証明書交付申請=COE)を行うことができません。もし、どうしても外国から告示外定住者ビザで呼び寄せしたい場合は、短期滞在など何らかの在留資格で日本に滞在し、「やむを得ない事情がある」として、告示外定住に変更申請する以外に方法がありません。ただし、そこまでやっても許可されない可能性は十分あります。
「定住者ビザ」の在留期間
「定住者ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月、または、日本の法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)があります。
在留期間は、日本での在留状況(届出をしっかりしているか、法律違反はないか、納税義務を果たしているか)、生活の安定性(秋雨にゅうがあるか)などによって、入国管理局さんが総合的な審査を行った上で外国人の方一人ひとり個別に決定されます。必ずしも希望する在留期間の許可がもらえるわけではありません。
最長の5年は誰もが希望しますが、在留状況が極めて良好で生計が安定している(何の問題もなく長く日本で生活できている)外国人の方がビザ更新を申請した場合などに、5年が許可される場合が多いと考えられます。
逆に、配偶者と離婚調停中で、配偶者と別居生活を送っている外国人の方がビザ更新を申請する場合などに、最短の6ヶ月が許可されることが多いようです。
「定住者ビザ」のQA
-
日本人と離婚した場合、必ず「定住者ビザ」をもらえますか?
-
日本人との離婚が成立してしまうと配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)は更新できません。しかし、日本人との間にお子さんがいて、そのお子さんを扶養をする必要がある場合、または長年日本に住み続けていて日本の生活に慣れ親しんでいる、などの理由で、引き続き日本への滞在を希望される外国人の方も多くいらっしゃいます。
その場合には、「定住者ビザ」へ変更できる可能性がありますが、配偶者との婚姻期間や離婚理由、お子さんの有無、子供の扶養の有無、日本の在留期間などによって総合的に審査されます。
この場合の「定住者ビザ」は告示外なので、必要書類や審査基準が公表されているわけではありませんので注意が必要です。
-
日本人の配偶者と離婚する予定で、現在協議中ですが、もうすぐビザの在留期限が切れます、どうすればいいですか?
-
日本人と結婚して配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ)を持っている外国人の方が、日本人と離婚してしまうと、配偶者ビザを更新できません。まだ離婚協議中で離婚が成立していない場合は「日本人の配偶者等ビザ」を更新することができる可能性があります。
なので、すぐに「定住者ビザ」へ変更申請するのではなく、まずは配偶者ビザの更新申請を検討しましょう。更新申請の際に、日本人の配偶者に協力してもらうのは難しいかもしれませんが、更新できる可能性はあります。ただし、現在の状況や事情を「理由書」などで入国管理局さんにしっかり説明する必要があります。
また、他の就労ビザ(技人国、特定技能など)へ変更する方法もあります。
-
私は日本人で、外国人の妻の連れ子を日本に呼んで一緒に生活したいのですが、できますか?
-
外国人配偶者のお子さん(連れ子)については、告示内で定められた「定住者ビザ」の種類に該当する可能性があります。ただし、連れ子であれば誰でも定住者ビザが許可されるわけではなく、原則、扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子である必要があります。
また、外国人配偶者さんに親権があるのか、これまでどのように扶養していたのか、日本に来てからどのように生活していくのか、などを「理由書」などでしっかり説明しないと不許可になってしまう可能性があります。
-
定住者ビザの申請は、許可されるまでどれくらい時間がかかりますか?
-
定住者ビザは他のビザと比べて入国管理局さんの審査に時間がかかる方です。長い場合は3ヶ月ほどかかることが通常です。また例年2〜3月にかけては、留学生の就職などでビザ申請が増える時期となり更に時間がかかる可能性があります。入国管理局さんが公開している情報では、2024年(令和6年)12月の「定住者ビザ」の審査処理期間は
・認定(外国からの呼び寄せ) 74.7日
・変更(他のビザから定住者ビザに変更) 42.7日
・更新(定住者ビザの更新) 34.6日
となっています。ご興味があれば、最新情報は以下のリンクから入国管理局ホームページをご覧ください。
-
定住者ビザと永住権の違いは何ですか?
-
定住者ビザと永住ビザ(永住権)は、就労制限がない(法律の範囲内であればどんな仕事でもできる)という点では同じです。
大きな違いは、在留期間制限があるかないか、です。定住者ビザは6か月、1年、3年、5年などの在留期限があり、更新手続きを行う必要があります。場合によってはビザ更新が許可されない可能性があります。永住ビザには在留期間制限がありまでん。
日本で長く生活している外国人の方の中には、永住ビザが取得できるのに定住者ビザのままの方もいます。定住者ビザと永住ビザの違いを把握して、より安心して日本で生活できるビザの申請を検討することをお勧めします。
-
定住者ビザから永住権は申請できますか
-
「定住者」ビザで日本に5年以上住んでいて、在留期間が「3年」または「5年」が許可されていれば、永住申請して許可される可能性があります。詳しくは、以下のページで解説しています。
「定住者ビザ」のまとめ
このペーでで取り上げる定住者ビザは以上となります。定住者ビザは非常に多くの事例があり、外国人の方お一人おひとりによって許可される事例も違います。

河野(かわの)
弊所ではビザ申請を丁寧に!早く!手続き致します。ご不明点があればお気軽にご相談ください。初回ご相談は無料! 福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。
以下では、定住者ビザに関連する情報をまとめています。是非ご覧ください。
外国人配偶者が離婚した後のビザは?|福岡の行政書士が解説
定住者から永住者へ|永住許可申請の要件と注意点|福岡の行政書士が解説
永住権の再申請は「不許可理由の分析」が最も重要|福岡の行政書士が解説
永住権を申請する際の「交通違反」の影響と対策|福岡の行政書士が解説
子どもを外国から日本に呼び寄せる方法|福岡の行政書士が解説
帰化申請と永住ビザ申請の必要年数まとめ|福岡の行政書士が解説
「定住者ビザ」最新の法務省告示(2021年10月28日)
「在留カード」の氏名を漢字にする方法とその確認方法
「不法就労助長罪」とは
永住権ビザ申請で「不動産」の所有は有利? 福岡の行政書士が解説
在留資格申請の「審査期間」について
河野尋志
かわのひろし
ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長
著者プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。