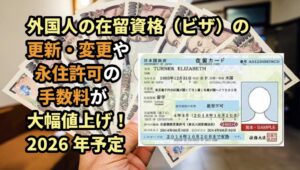(更新者:国際行政書士 河野尋志)
技能実習制度(技能実習ビザ)が「育成就労制度」(ビザ)へ変わります。
近年、日本の人手不足が深刻化している中で、国際的な人材獲得競争が激化しています。また、これまでの技能実習制度では、制度目的と実態のかい離(技能を教えるという建前だが、実際は労働力の確保)や、外国人の方の人権が侵害されるなどの問題が指摘されていました。日本国内の人手不足への現実的な対策のーつとして、外国人の方の受入が欠かせない状況にあります。であれば、外国人の方にとって魅力ある制度を構築することで、我が国が外国人の方から「選ばれる国」となり、我が国の産業を支える人材を適切に確保することが重要だと日本政府は考えています。
現状を受けて、日本政府は2024年(令和6年)6月、国会で入管法など法律の改正をしました。この法改正では、技能実習制度を無くし、人材育成と人材確保を目的とする「育成就労制度」を創設し、これまで技能実習制度において指摘されてきた課題を解消するとともに、育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人の方が日本で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、長期にわたり日本の産業を支える人材を確保することを目指すことを目的に設定されています。
とはいえ、改正された法律が施行されるのは2027年の予定で、それまでは移行期間になり、まだまだ時間がかかります。このページでは、現状(2025年1月現在)で分かっている技能実習制度の概要を紹介しつつ、現状把握の意味で「技能実習ビザ」と「特定技能ビザ」の違いをまとめてみました。外国人の方だけでなく、受入機関の皆様にも参考になれば幸いです。
技能実習ビザから育成就労ビザへ
「技能実習ビザ」と「特定技能ビザ」の違い
実は、特定技能ビザを持つ外国人の方の約半分はもともと技能実習ビザで在留していたことが2024年までの統計で分かっています。それほど特定技能と技能実習は密接に関係していることから、以下で2つのビザの違いをまとめてみました。
| 項目 | 技能実習ビザ 1号 2号 3号 | 特定技能ビザ 1号 2号 |
|---|---|---|
| 目的 | 先進国としての役割を果たすため「技能」「技術」「知識」の移転を通して発展途上国の経済発展に協力する ●労働者として扱うことができない | 生産性向上や国内人材を確保するための施策などを行っても、なお人材不足が深刻な業種の労働力を「一定の専門性・技能をもつ外国人材」によって補う ●労働者として扱うことが認められている |
| 機関・団体 | ●監理団体(組合)(全国に約3,600ある/非営利団体のみ) ・「外国人の方々」への入国前後のフォローをする機関 ・「受入れ機関が技能実習法に基づいた適正な制度運用をしているか」を確認・指導するために監査や訪問をする機関 | ●登録支援機関(全国に約7,500ある) 「支援計画の策定」が義務であるため、特定技能制度で定められた「外国人の方々」への支援業務を、「自社で支援を実施できない受入れ機関」の代わりに「外国人の方々」への支援業務をする機関 ※2号では「支援計画の策定」は義務ではない |
| 業種と職種 | 86職種・158の作業(基本的には1つの作業への従事のみ) ※業務内容の自由度が低く、試験準備などのために受入れ後の手間暇も多くかかる | 特定技能制度で認められた16分野 |
| 求められる要件 | ●なし ※介護のみ、入国時に日本語能力試験N4が必要 | ●日本語能力(N4以上、またはJFT-BasicでA2以上) ●各分野・業務区分で定められた技能試験の合格 ※「介護」分野では、日本語要件として介護日本語評価試験の合格も必要 ※2号は、日本語能力試験はない |
| 他の就労ビザへ変更 | ●1号はできない ●2号では、できる可能性あり →「技能実習2号ビザ」(3年間)を良好に修了した外国人の方は「技能実習ビザと同様の業種・職種」で「特定技能ビザ」の技能試験と日本語試験を免除された上で「特定技能ビザ」を取得できる。 →技能実習時と異なる業務を行う場合でも、技能実習2号を良好に修了している場合は日本語試験が免除されます。 ※2024年現在で、特定技能ビザを持つ外国人の方の約半分は、もともと技能実習ビザ | ●できる可能性あり ※例1 ❶通信制の大学で学位を取得、またはN2以上合格 ❷技能実習生への通訳業務で実務経験を積む ❶❷を満たせば技人国ビザの国際業務(通訳者)に変更できる可能性あり ※例2 「介護」分野で就労中に「介護福祉士」の資格を取得することで「介護ビザ」への変更できる可能性あり |
| 転職の可否 | ●原則不可 ・受入れ機関の倒産など、やむを得ない場合は受入れ機関の変更が可能 ※2号から3号へ変更する場合だけ受入れ機関の倒産など、やむを得ない場合に(転職ではなく)受入れ機関の変更が可能 | ●できる ・特定技能ビザで就労している機関と「同じ業種・職種」の機関への転職はできる。 ・「別の業種・職種」に転職したい場合、特定技能ビザの技能試験に合格し技能要件を満たしていれば転職可能 ※要件を満たしていれば、比較的短期間で転職することが可能 |
| 受入れ可能人数 | ●制限あり ・最小の場合 「受入れ機関の常勤職員数」が30人以下の場合、受入れ可能人数は3人 ・最大の場合 「受入れ機関の常勤職員数」が301人以上の場合、常勤職員数の20分の1 | ●人数枠の制限なし ※介護・建設は上限あり(常勤職員数と同数以下) |
| 最長在留期間 | 1号:1年間 2号:2年間 3号:2年間 ※合計して最大5年間の技能実習が可能。技能実習ビザから特定技能ビザ(1号)へ変更して合計した場合、最大で10年間、日本に在留することが可能 | 1号:最長5年間 2号:実質無期限 |
| 家族帯同(家族呼び寄せ) | できない | 1号:できない 2号:できる(配偶者、子が対象。親は不可) |
| 永住ビザを取得するための「直近の5年間、就労資格を持って在留していること」の期間の対象になるか | 対象外 (永住ビザ要件の「引き続き10年以上日本に住んでいること」の期間の対象にはなります) | 1号:対象外 2号:対象になる (1号も2号も永住ビザ要件の「引き続き10年以上日本に住んでいること」の期間の対象にはなります) |
| 受入れ機関(会社や団体)の視点から考えた場合場合 | ●メリット ・基本的には転職できないので、雇用が安定する ・求められる要件がないため、比較的簡単に人材を集めやすい ・特定技能ビザと比べると、若い人材が多い ■デメリット ・入社までの期間が、面接から入社までに半年以上はかかる ・受入れ初期にかかる費用や、定期で支払う管理費用などを含めると特定技能ビザの外国人の方よりも多くの費用がかかる ・特定技能外国人の受入れと比べて手続きの手間がかかる | ●メリット ・技能実習ビザと比べると、受入れ後の制約が少ない ・雇用契約期間を自由に設定できる ・入社までの期間が短い 国内人材の受入れも認められている特定技能では,2ヶ月程度での入社実現も可能 ■デメリット 直ぐに転職する可能性がある |
育成就労の概要
厚生労働省と出入国在留管理庁の連名の資料に、育成就労制度の目的は、日本で3年間の就労(育成就労)を通じて「特定技能1号水準の技能を有する人材を育成」するとともに「当該分野における人材を確保すること」と明記されました。
また「出身国の送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みの導入」などを行うことで送出しの適正性を確保し、「就労後の転籍を一定の要件の下に認める」ことなどにより労働者としての権利保護を適切に図る、とも記載されています。
上記の通りになれば、日本で働きたい、働き続けたい、と思ってもらえる状況になる可能性を感じます。以下では、参考までに2029年(令和9年)に改正法が施行されるまでのスケジュールとイメージを貼り付けておきます。



[FAQ]育成就労制度について
-
育成就労制度とは何ですか?
-
日本の特定産業分野において、外国人を育成しながら必要な人材を確保する新たな在留資格制度です。技能実習制度の課題を解消し、外国人が就労を通じて技能や日本語を習得し、特定技能へ移行することを目指しています。
-
なぜ育成就労制度が導入されたのですか?
-
能実習制度は人材育成を目的としていたものの、実態として労働力確保に偏っていたため、外国人の権利保護や転籍の柔軟性を高める制度に見直す必要がありました。
-
施行日はいつですか?
-
改正法の公布日(令和6年6月21日)から3年以内に施行されます。正確な日程は今後、政府から発表されます。
-
育成就労制度では何年間働けますか?
-
原則3年間の在留が認められています。試験に不合格などの理由がある場合は、最大で1年の延長が可能です。
-
特定技能への移行は可能ですか?
-
はい。育成就労期間中に技能と日本語の試験に合格すれば、特定技能1号への移行が可能です。
-
転職はできますか?
-
原則として転職は制限されていますが、同一業務区分内で、一定の就労期間・技能水準を満たす場合、本人の希望による転籍も可能です。
-
どのような分野で育成就労が認められますか?
-
農業、建設、製造などの特定産業分野で、国内人材確保が困難で、技能を習得させる意義があると認められる業務が対象です。分野の詳細は主務省が決定します。
-
どの国から受け入れ可能ですか?
-
原則として、日本と協力覚書(MOC)を結んでいる国からの受入れが対象です。悪質なブローカーを排除するためです。
-
現在技能実習生を受け入れている企業はどうなりますか?
-
改正法の施行日前に申請し、施行日から3か月以内に実習を開始した場合は、引き続き技能実習の受入れが可能です。
-
監理団体はどうなりますか?
-
育成就労では「監理支援機関」が設置され、より厳格な監査要件が課されます。外部監査人の設置などにより中立性が確保されます。育成就労制度における外部監査人の役割については以下のページで解説しています。
-
受け入れ形態は?(単独型と監理型)
-
外国の子会社や支店の社員を受け入れる「単独型」と、監理支援機関が関与する「監理型」があります。取引先企業の社員は「監理型」のみで受け入れ可能です。
-
送出機関への手数料は?
-
外国人が送出機関に支払う費用が不当に高額とならないよう、制度的にチェック機能が設けられます。
以下は、育成就労に関する情報をまとめた記事リストです。参考までにご覧ください。
このページでの記事は以上です。今後、育成就労制度については様々な動きがあると思いますので、随時更新して参りたいと思います。

河野
(かわの)
ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料!オンラインでの面談にも対応しております。
以下では、技能実習ビザの関連情報をまとめています。
帰化申請と永住ビザ申請の必要年数まとめ|福岡の行政書士が解説
資格外活動許可について
「在留カード」の氏名を漢字にする方法とその確認方法
「所属機関等に関する届出」とは
「不法就労助長罪」とは
日本で働く外国人を海外から呼び寄せるCOE手続き
在留資格申請の「審査期間」について
河野尋志
かわのひろし
ビザ申請サポート福岡 外国人支援センター
国際行政書士 河野尋志 事務所 所長
著者プロフィール
企業の取締役として外国人の社員さんと一緒に国際業務に取り組んで15年間、多くのインバウンド事業や外国語ツール(多言語ツール)の作成、貿易業務の調整に取り組んできました。行政書士業務を始めてからは、様々な在留資格(ビザ)の申請経験も重ねてきました。外国人の皆さんの気持ち、日本の行政の考え方、企業の管理者の立場を考えてサポート致します。どうぞ、お気軽にお問合せください。
●資格:行政書士・通関士有資格者・総合旅行業務・国際ビジネス法務
●個人:宮崎県出身、1976年生まれ、1男2女の父、柔道3段(今は3級くらいの実力)

弊所のサービス内容や価格、手続きの流れ、許可の可能性診断につきまして無料相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。福岡を中心に、九州、全国対応が可能で、オンライン(ZOOM、LINE、WeChat、Teamsなど)での面談も対応しております。